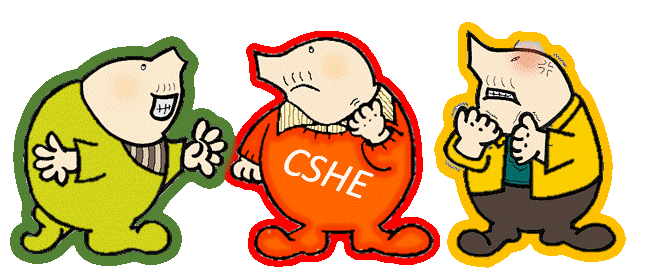University Teaching 日本の大学院で英語で授業するとはどういうことか 国際開発研究科
平成11年の4月にこの研究科に赴任してから、10ヵ月が経とうとしている。私は前期、後期ともに講義、ゼミともに2コマ続きの授業を行ない、半期で単位を出すようにしている。前期は英語による講義、後期は日本語を中心に時折英語を入れての授業を行なっている。本研究科の授業を英語でやるか日本語でやるかということに関しては、本研究科でもさまざまな議論がある。私が英語で講義をしていた前期、どちらかと言えば、「なぜ英語なんかでやるの」という意見の方を同僚の先生から言われたことの方が多かったように思う。あるいは、自分が批判されたことの方が記憶に残りやすかったため、こう感じているのかもしれない。
この反対意見の言い分は、主として、日本の教育機関で教育するのになぜ日本語でやらないのかという単純明解なものである。大学院国際開発研究科は、院生のほぼ半数が留学生である。「彼らは日本に来て、日本語をマスターして自分の国に帰らなければ、いったい何のために日本に来たのかということになりはしないか」という議論が、英語で授業をすることへの批判の中心にある。たしかにこの理屈はそれはそれで筋が通っているように思われる。しかし、本当にそうだろうか。英語で授業する理由
私の場合、前期の講義を英語でやると決めたが、それにはいくつか理由がある。第1に、何を教えるかという内容から来るものである。私が英語で教えたのは、いわば国際政治学で、しかも中東のケーススタディを入れながらの講義である。国際政治学はアメリカで発達した学問であり、理論的な枠組みもほとんどすべてが欧米で開発されたものである。さらに中東の事例研究となると、古い時代はともかく、現代の中東の政治となると、これもまた欧米特にアメリカの方が日本よりかなり研究は進んでいるように思われる。そうすると、教科書にしても補充資料にしても、英語で書かれたものの方が日本語のものよりはるかに多く、かつ、理論的な枠組みとなっている専門的な概念はほぼすべて英語で確立されたものということになる。そうした状況では、英語で講義した方がはるかに効率がよく、概念の整理をするうえで翻訳によっておこる意味のズレもなくなる。
第2に、国際開発研究科に入ってきた留学生は、日本人と同等の日本語能力をもっていることを前提とするような試験体制で入学してはいない。そうした学生に対して、日本人の大学院生とほぼ同じレベルの日本語の語彙能力があることを前提に授業を行うのは、やはり望めないように思われる。一定の時間的制約の中で、中身のある授業をしようと思えば、英語で行なったほうがはるかに情報量が多くなる場合もある。
第3に、本研究科では、日本人の場合、将来国連などの国際機関で仕事をすることができるような学生を養成するという目標が、教育目標のひとつにある。国際機関での仕事は競争がひじょうに激しいため、現実的に何人の学生が本当に国際機関で職が得られるかは別としても、今や英語でコミュニケーションができるかどうかというのは、国際化の進展とともに当然のこととなっている。ゆえに日本人の学生に対しても、英語で授業を行うことは意味があるように思える。
つまり、教える内容がどのような学問的発展の経緯を経ているかということ、留学生の院生を受け入れる基準がどれだけ日本語の堪能さを前提にしていうかということ、さらに、国際社会における英語コミュニケーションの重要性を、国際開発という分野がどの程度認識すべきかといった問題を考える必要があるのではないかということである。
こうした前提で、英語で授業をやってみたが、問題はいくつか出てきた。ひとつは、留学生のうち英語を母国とする学生がひと握りしかいないことである。留学生のほとんどが、アジア、アフリカの学生で、そのなかでも中国人や東南アジアなどの学生が多く、個人差はあるが、あまり英語が得意でない学生がかなりいることがわかった。そうした学生は、英語のテキストを使って英語の講義を行い、さらに英語でディスカッションをするということになると、どうしても逃げ腰になる。英語の授業も、特に課題が多いと、学生によっては日本語を読むのと同じくらい負担になる場合もあるのである。
英語で自己主張できない理由
もうひとつの問題は、日本人の学生が議論になかなか参加できないという傾向である。これは単に学生の英語の能力云々だけの問題ではない。日本では自分の議論を堂々と言って、他人と議論するという教育が、小学校から大学に至るまでほとんどなされていないのである。議論するには、ある一定の自己主張ができるかどうかが前提となる。日本人は、個人差はあるとはいえ、自己主張は世界のなかでは弱い方に入るのではないかと思う。
私自身、アメリカでの留学時代は、自己主張ができなくて苦労した。専攻が中東の現代政治であったため、アメリカ人ですらマイノリティーになるほど中東出身者が大多数を占めるような環境に身を置いていた。口から生まれたのではないかと思えるほど、自己主張の強い中東出身者に押され、いつ自分の意見を言おうか待っていると授業が終わっていたという始末であった。しばらくして、人の話をさえぎって質問や意見を言わない限り、チャンスはないということに気がついたが、人の話が終わらないうちに口をはさむなどという勇気はなかなか持てなかった。
外国語を話すということは、その言語の文化で話すということは言うまでもない。英語のように、主語を決して省略できない文の構造とは、自分の意見を言うには、常に「私は」「私が」と言わなくてはならない、自己主張の強い文化的背景が、言語のなかにすでに潜んでいるわけである。つまり、自分の性格も変えないと、外国語でのコミュニケーションというのはできない、という面すらあるように思われる。
英語で授業をする私にとっても、英語が母国語でない留学生や日本人の学生にとっても、英語は第二外国語である。外国語でコミュニケーションは、お互いにそれなりのむずかしさはある。しかし、国際化が進展している今日、日本人、外国人が同時に向かいあって授業を受ける環境では、国際的には共通語として了解されている英語を媒介にコミュニケーションする以外には今のところ他に方法がないような気がするのである。日本史や日本文学を教えるのであれば、絶対に日本語で教育しなければいけないとか、留学生も日本語を完全にマスターしなければいけないとか言って、英語での教育に反対してもいいかもしれない。でも、「国際開発」研究科という「国際性」が問われる大学院では、英語は教育のための道具であると割りきって考えた方がいいように思われる。