第20回招聘セミナー 授業レポートを通した生徒から学生への移行プロセスの検討 長野 剛 氏 九州大学大学教育研究センター 助教授 2001年 3月14日(水) 13:00-16:00 名古屋大学東山キャンパス センター会議室
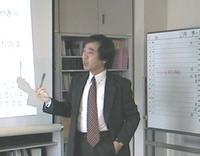
九州大学の新入生の一部について、進路選択決定の際の指標として何を用いたかで分類し、授業レポートの記述に関する調査を行った。指標については、「受験学力や偏差値による進路選択をした学生(A群)」と「興味・関心による進路選択をした学生(B群)」とに分類した。その結果、A群については、大学の講義に対してネガティブな認識をもっているのに対し、B群はポジティブな認識をしている傾向があることが分かった。また、「何かいいことがあるのではないか」(報酬的興味)「能力を試してみようか」(評価的興味)といったものに過敏になっている傾向があり、「なぜ」から「何」「いかにして」といった、関心に根ざした問いかけが不得手な学生が多くなっている。筋道をたどった判断や二者択一的判断は受験でトレーニングされているようであるが、観察による事実収集の能力や留めおくことによる洞察をする能力について不足している学生が多い。この点を共通教育でトレーニングすることが、生徒から学生への移行プロセスを考える上で重要な点と言えよう。
